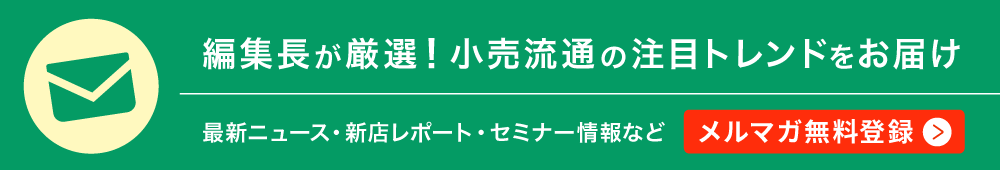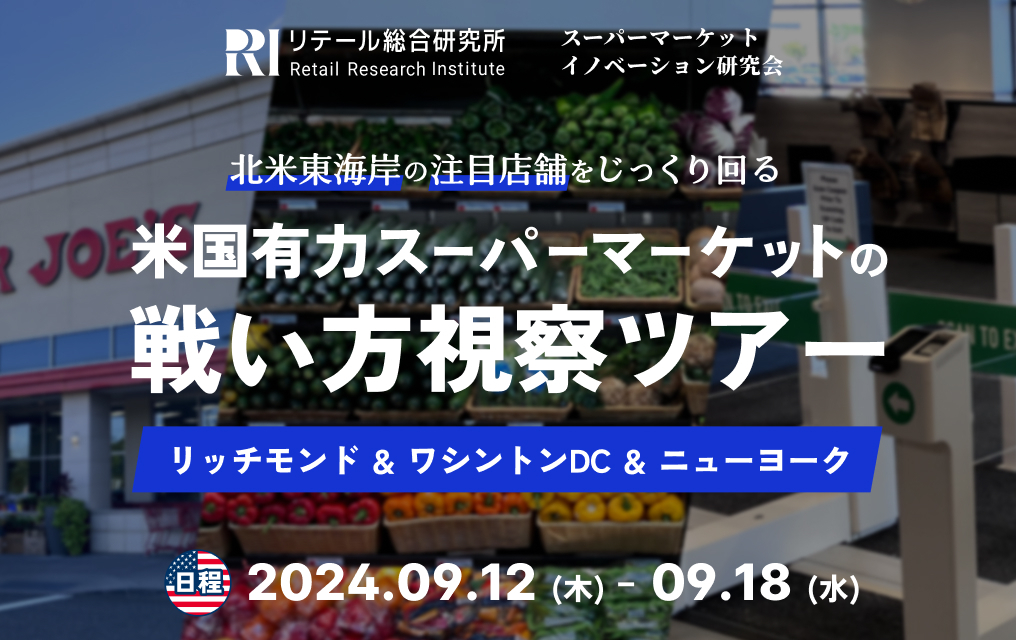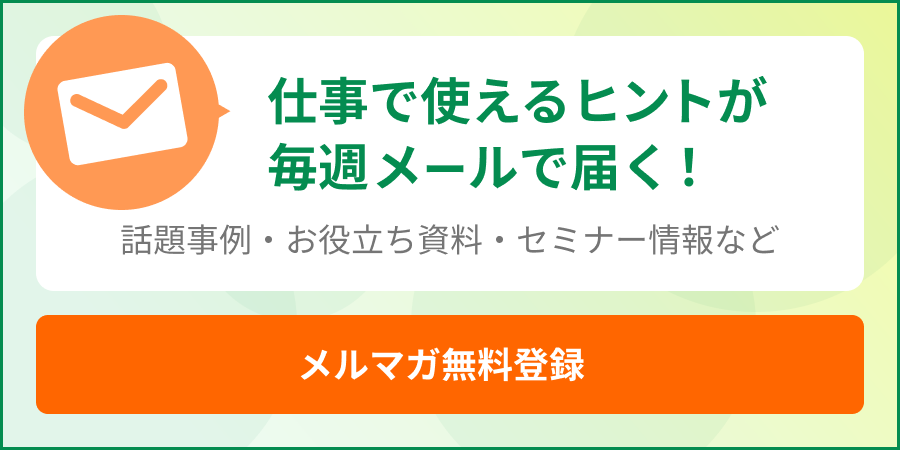「アヌーガ2021」レポート第2回 コロナ禍の影響が食品トレンドに色濃く反映
2022.04.12
2021.12.28
2020年の春から世界中に大きな影響を及ぼし続けている新型コロナウイルス。今回のアヌーガの展示を見ると、その影響が少なからず反映していることを実感できる。
その大きなものが「サスティナビリティ」の存在感の大きさだ。もちろん、サスティナビリティは新しい概念ではない。しかしながら、今回のコロナ禍によって在宅時間が増え、改めてこれまでの消費について見つめ直した傾向は世界的なものであったようだ。
特に日本では20年、イオングループのビオセボンやライフコーポレーションが手掛けるビオラルといった有機やサスティナビリティを打ち出したフォーマットの売上げが急増した傾向が見られた。
今後の世界にとっては重要である半面、経済効率としては必ずしも高くない側面も持つこうした分野は、通常の商品と比べた価格差の問題もあって、特に日本においてはこれまで一部の動きにとどまっていたといって良いだろう。
20年、食品という必需品を取り扱うスーパーマーケットは、特需によって大きく売上げを伸ばしたが、ビオセボンやビオラルの売上げはそれを大きく上回る伸びを示した。
ビオラルはライフコーポレーションが将来を視野に入れた投資の意味も含む戦略的な事業であったが、それまで5年ほど赤字続きだった同事業が20年に一気に黒字転換したことは大きなトピックといえた。
すでに世界レベルでは何年もの間、急増する人口に対してどのように食品を提供していくかが大きなテーマとして議論され、例えば食肉など動物性のものと比べ環境負荷を大幅に削減できるプラントベース(植物性)の食品に関心が高まるといった動きもあったが、こと日本では「これから」といった要素が大きかった。
それが大きく変わったことが実感できるのは、今回のコロナ禍の影響といえる。
22年につながる食品の3つのトレンド
それでは今回のアヌーガではどうか。
アヌーガで食品の最新トレンドを発信しているイノーバ・マーケッツ・インサイツが掲げる内容を中心に読み解いてみよう。
同社は毎年、食品のトレンドを発信しているが、今回のアヌーガで22年のトレンドとして3つの項目を挙げた。
1つ目は、「プラントベース(植物性)のイノベーション」。
より環境に配慮した商品であることが重要になってくる中、どこで取れたものか、農家にも配慮されたものかといったトレーサビリティやサスティナビリティといった要素が重視されるようになる傾向がみられる中、植物性の食品は引き続き増加し続けている。
昨今、急激に伸びた分野だが、その傾向は変わっておらず、さらに進化している状況にある。例えば日本では大豆が中心であるが、ミルクではアーモンドなどさまざまな代替食品が登場し、さらにその中で次第に絞り込みが行われているような段階であるという。
今回、代替食品では多様な展示が見られたが、これまで多くが牛肉などを模した代替肉、もしくは代替ミルクであったが、次第に「代替魚」「代替チキン」といった新たな方向性が出てきていることは大きな特徴だった。
エンドウ豆、大豆、ヒヨコ豆、レンズ豆などで魚に模した商品を開発している出展者はその意図を「水産資源を保護する」と語る。背景には環境保護の考えがある。同社の商品はアメリカやヨーロッパでは小売業ではすでに取り扱いがあり、シンガポールではレストランでの取り扱いも始まっているという



これらは代替食品の多様性を示すと共に、健康軸とも連動する動きといえる。実際は同じ代替肉ではあるが、その中でもより健康のイメージに近づいていると見ることができるからだ。



実際、コロナ禍の巣ごもりの影響もあって、栄養など機能性に対する関心が大きく高まったとされ、栄養などを付加した機能性の商品が大幅に増加している。
それとも関連するが、イノーバが掲げる2つ目のトレンドが「食卓にも押し寄せる新たな技術」。
コロナ禍という危機があったことで新しい技術の開発が進み、イノベーションが進んだ側面もあるだろう。栄養素を濃縮した食品、疲れに対して回復が見込める食品なども技術の発展も相まって登場する傾向がみられるという。


特に「腸」に良い食品に注目が集まっているという。繊維に由来する成分、例えば海藻といった、海外ではこれまであまり注目されていなかったものを見つめ直すような動きも見られる。
また、自宅にいる機会が増えているからこそ、精神の安定という側面も注目されているという。健康的に年齢を重ねるために改めてスポーツなどに取り組むといった動きも、コロナ禍の生活からすれば納得できるものといえるだろう。
いずれにしても食品における機能性を重視し、そこにはお金をかける傾向がみられるといい、それは日本でビオセボンやビオラルの売上げが伸びていることとも一致する。その中では技術的に機能性を加えたものだけでなく、自然由来のものも加えた形でニーズに合わせて取り入れるといった消費の姿が見えてくる。
また、コミュニケーションツールが発展したことによる消費者との会話、さらに消費者同士の会話が発展したことが、さらにこれらの消費傾向に拍車をかけているとみることもできる。
イノーバのトレンドの3つ目が「機会のシフト」。
食品をどのように取るかというチャネルの問題では、これまで存在感が大きかったレストランが減り、他の業態、例えば宅配などに移り変わるといった傾向の他、これまで主にレストランで味わっていたような美食を自宅で楽しめるような食事セットなどが登場し、それらを宅配で購入し、オンラインで懇親会をするといった新たな形の食事が登場したことも大きな特徴となっている。
イノーバではその一例として、オランダのケンタッキーフライドチキンが展開している「スパイシー・チキン・ボールズ」を挙げている。同商品はフライドチキンともチキンナゲットとも異なる「ボール状」の商品。
今回、同商品に限らずフィンガーフードにもなる「ボール」の商品が目立っていた。イノーバではコロナ前から、若年層を中心に、はっきりとした「3食」があいまいとなり、軽食を作業などをしながらつまむ「スナッキング」の増加を指摘していたが、今回、食の機会が増加する中でのスナッキングの進化がこうしたボール型商品の増加に表れているといえるかもしれない。



世界を視野に入れる日本の出展者
アヌーガは世界から食品に関する商品、情報が一堂に集まるイベントのため、当然、日本からの出展もある。日本の企業が出展する場合、単独で出展するケースもあるが、ジェトロ(日本貿易振興機構)が取りまとめた「ジャパンパビリオン」として出展するという2つの方法がある。
ジャパンパリビオンは前回、19年の出展は70者以上だったが、新型コロナウイルスの影響を色濃く受けた今回は32者だった。日本帰国後の隔離というハードルがあるため、ジェトロとしてもヨーロッパに拠点ある、もしくは代理店を持つ事業者を中心に募集したこともあるが、主催者側のケルンメッセからコロナ対策としてブース面積を通常9㎡のところ12㎡としていることもあり、出展者を絞らざるを得なかった面もある。
それでも世界に向けたリアル展示会にこれだけの出展があったことは重要だ。さらに32者のうち12者は日本から人員が訪れての出展だった。
ジュエトロのデュッセルドルフ事務所の木場亮次長は、ジャパンパビリオンの反響について、「とても良い。来場者は19年に比べて少ないが、真剣度の高い人が多く、商談の質が高い」と語った。コロナ下でもあえてリアル展示会に訪れる来場者はそれだけ熱心であるということだろう。
ジェトロとしても新型コロナウイルスが発生してからは、初の海外での大規模な展示会となった。

ジャパンパビリオン出展者の1つ、流通サービス(静岡県菊川市)は独自性あるビジネスで、今回の出展の傾向とも同期している企業の1社だ。
もともと緑茶の生産者だが、生産から販売まで一気通貫で手掛けていることが特徴だ。日本の人口縮小傾向を受け、10年ほど前から海外に販路を築いてきた。
8年前からは畑の上に太陽光発電を設置し、発電しながらの農業もするというモデルを確立。緑茶は日照を40%ほど抑えた方が品質が良くなることから、その性質を活用。また冬は霜が当たらない、夏は温度が上がらないなど、それ以外にもメリットがある。性質を生かしながらサスティナビリティのある農業の形を築いた。
緑茶の海外輸出量は大幅に伸びている一方で、耕作放棄地は増加傾向にあるという。そうした中、同社としては耕作放棄地を借りながら拡大中。今後、世界をターゲットに緑茶のシェア向上に励むと意気込む。

一方、キノコ関連の事業を主力とするホクトは、ジャパンパビリオンではなく、独自に出展した。ビジネスとして日本からの輸出ではなく、ヨーロッパに工場を設置しての現地生産を視野に入れているため、「日本の商品」を打ち出すというよりは、あくまでキノコという商品自体を打ち出すことに狙いがあることも独自出展した理由の1つだという。
すでにアメリカのカリフォルニアにオーガニックの工場を設置するなど世界展開を実践しているが、今回はそれをヨーロッパにも拡大することも視野に入れている。まずはアメリカで生産した商品を持ってきてヨーロッパでのマーケティングに取り組むとの意図で今回出展した。
エリンギなどはドイツでも使われることがあるというが、他品種はまずは商品紹介からのスタートといった段階だが、その分競争がないというメリットを生かし、世界展開を強化していく。
世界的な展示会は、バイヤーにとっては世界中の商品に触れる機会であると同時に、サプライヤーにとっては、世界を視野にビジネスを拡大する機会にもなる。日本の出展者はもちろん、出展全体を見ると、そこには自社の強みを認識した上での差別化戦略を実践すると同時に、世界のトレンドも踏まえるという二重の戦略が共通項として見えてくる。
世界中が新型コロナウイルスという困難の経験をへた上で開催された今回のアヌーガは、リアル展示会の価値を改めて見直すきっかけにもなっただけでなく、コロナ禍で起こった状況が、日本で起こったことを含めて、ある程度世界共通のトレンドを生み出していることが確認できる機会となった。
主催者インタビュー
ケルンメッセ チーフ・オペレーティング・オフィサー(CEO)
オリバー・フレーゼ氏

「コロナ禍で改めて持続可能性、健康、コンビニエンス、デジタルに焦点、そこに新たなテクノロジーがイノベーションを起こす」
——今回のアヌーガのテーマは、「トランスフォーム」だ。そこに込めた思いは。
フレーゼ 食品産業のメガトレンドがある。持続可能性、健康、コンビニエンス、デジタル化だ。
コロナの関係で、改めて認識したのはグローバルで変化が起きていること。100億人にならんとする多くの人間がいることが意識されてきた。その中で地球環境の変化と共に持続可能性についても考える。さらにデジタル化。それらがフォーカスされてきた。
その中で、展示会の開催者として食品産業にも変化(トランスフォーメーション)が必要だと考えた。その中で、イベントについてもショーやフォーラムを変化させた。
——アヌーガの独自性、他の見本市と差別化できる点は何か。
フレーゼ 一番ユニークであるのは、1つ屋根の下に10の展示会があること。さらに多様性が食品の中で紹介されていることだ。
おもしろいのは、大企業だけでなく、中小企業にもフォーカスを当てている点だ。つまり、国際的でもあるが、国内的でもある。展示者は世界中から100カ国以上、訪問者もそれ以上の国から来ている。100年を超える歴史があり、食品・飲料品の世界で一番の展示会であると自負している。
また、展示会の将来の可能性を考えてきたが、今回、その1つとして、オンラインとリアルを掛け合わせたハイブリッドの展示会としたことも特徴だ。来場した人はもちろん、来場できなかった人にも全てネットワークができる可能性が拓けた。トピックは全てデジタルでも知ることができる。
このハイブリッドの展示会のやり方は将来にわたって続ける。2020年にはできなかった部分も多いが、その2020年の間に蓄積し、このハイブリッドの体制を築き上げた。来場しない人にも見てもらえる可能性が増えたことは、展示者にとっても大切なことだ。
——新型コロナウイルスにどう対じしたか。
フレーゼ もちろん、大変だった。20年2月から(事業は)ずっとストップしていた。雇用者としては従業員に対して責任が取れないし、モチベーションを保つことが大変だった。計画しても、結局、延期になったり中止になったりして、すごく大変だった。
ただ、その中でも投資もしてきた。1つは会場を拡張し、会議室などを作った。また、デジタルにはかなりの投資をした。
——オンラインとリアルとのハイブリッドで期待することは。
フレーゼ アヌーガとしては初めてのハイブリッド形式だが、ケルンメッセとしてはこれまで2つの展示会をこの方式を実施した。経験から得たことは、まず、食べたり、嗅いだり、触ったりといったことができるリアルの展示会の代わりになることは無理だということだ。
しかし、リアルに「追加」することは可能だと分かった。デジタルを通じて知り合いになり、会話をするといった新しいネットワークができるなど可能性が広がった。

——食品産業に新型コロナウイルスが与えた影響をどう考えるか。
フレーゼ 食品産業の不安定さが、コロナによってはっきりしてきた部分はあるのではないか。「グローバルの生産で果たして良いのか」といったことを考えるきっかけになった。例えば商品が世界中から来るということではなく、「地産地消」を見直すといったことだ。
消費面では、近所の農家が何を作っているのかを意識したり、あるいは自宅にいるなど行動が制限されることによって、利便性、自分たちの食べ方、消費の仕方を再確認することになった。無駄なものを捨てないようになるといったことも意識するようになった。これまでの価値が変わっていく可能性が出てきた。
また、産業としては消費者が家で調理をすることが増えたため、ミールキット、セット、宅配、宅配のためのアプリ、そのためのスタートアップのような会社も登場した。つまり、家庭で調理するための市場が活性化した。
これまでは「便利」であることが大きな要素だったが、それだけではなく家にいることで改めて健康が意識されたり、天然素材を用いることが重視されたり、中見だけではなくパッケージでもサスティビリティが要求されるようになってきた。
外出を控えることを余儀なくされ、外食もできず、改めて近所に買物に行った際に、地域の商品を再確認できたこともある。(グローバルに広がった)自分たちの意識が「身の回り」に戻ってきた。
この間、ケルンメッセでは家具や調理用品の展示会を開催したが、ものすごい反響だった。旅行に行けなかったことから、お金がそこに向かったということもあると思う。
——今回、代替食品やフードテックの存在感がかなり高まっている。
フレーゼ 代替食品の市場は、将来にわたってかなり高い可能性を持っていると思う。実際に成長する産業であることが分かっているので、投資も大きくなっている。テクノロジーもそこに関連している。
アヌーガでも、それらのイノベーションが反映されていて、代替肉、代替魚、代替チーズ、代替パッケージなどにフォーカスしている。全体として、魚介類の市場がかなり増えてきている。
それと同時にテクノロジーを持つスタートアップなど新たなプレイヤーが、食品産業に新しいイノベーションをもたらせてくれると思っている。そのプラットフォームとして22年に「アヌーガホライズン」を実施する。
それに伴って、それら個々の要素をつなぎ合わせ、全体の体系を作って行く可能性を広げていきたいと思っている。
——アヌーガホライズンとアヌーガはどのような関係となるか。
フレーゼ アヌーガホライズンは、アヌーガと同様に隔年で、時期は9月。アヌーガは、コンセプトとしては、展示者がリアルの商品を、バイヤーをターゲットに展示するもの。それに対して、アヌーガホライズンは、現在ではなく5年後、10年後の将来に向けたもの。今後のパートナーを探しに行く場所だと考えている。ターゲットはバイヤーも含むが、ビジネスを開発する人、戦略を考える人などになる。
アヌーガホライズンには、展示そのもの、会議、そして経験の3つのポイントがある。「食品産業の実験室」のようなものになるはずだ。

——今後、どのようなことに注目しているか。
フレーゼ 第一に期待しているのは、普通に展示会ができること。その意味で、今回は本当に安心した。また、技術的なトランスフォーメーションのセクターが活発化しているので、そこに期待したい。
——日本のバイヤー、サプライヤーにメッセージを。
フレーゼ 今回、残念ながら会場に来られなかった人が多いと思う。その意味でオンライン展示会のアヌーガ@ホーム(https://www.anuga.com/trade-fair/anuga-home/)のサイトを本当にお勧めしたい。これを活用することで、(会場に来た機会だけでなく)継続的な営業活動が可能になる。
同時に、今回出展している日本からの36の出展者には本当に感謝している。素晴らしいことだ。アヌーガ23年のときは、コロナ前の19年の状態に戻ることを期待している。
日本の企業は、全体的に技術的なレベルが高い。その意味でもぜひ、アヌーガホライズンに参加してもらいたい。