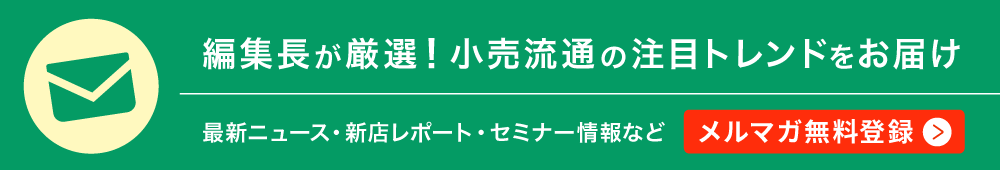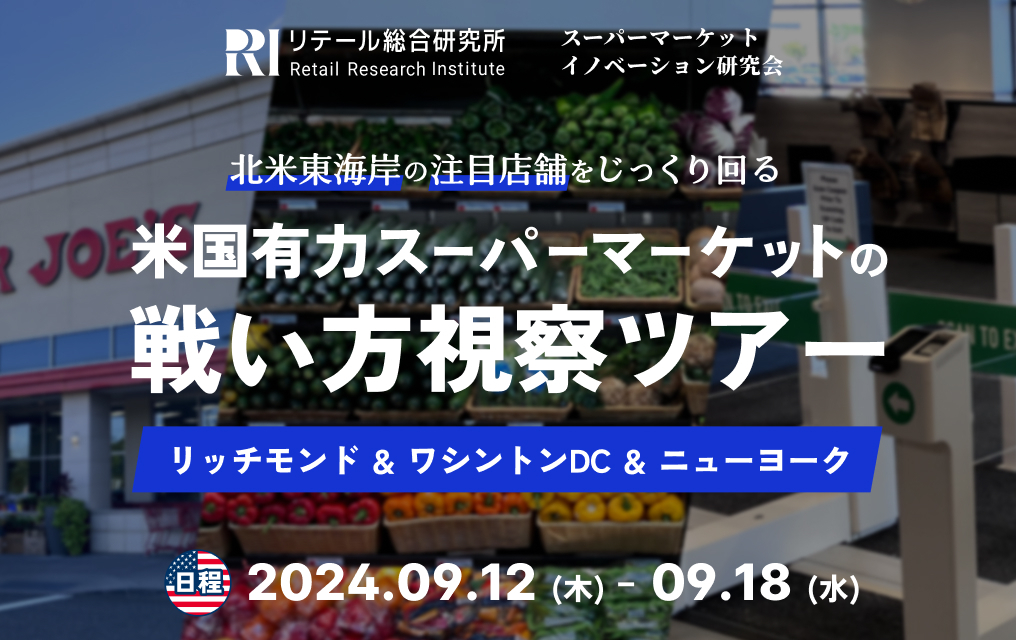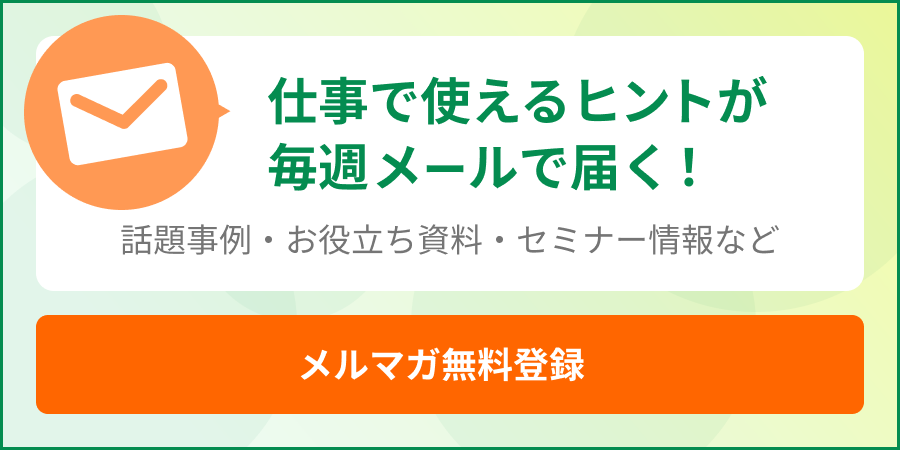ダイバーシティの効果とは?メリット・デメリット、先進企業の取り組み事例などを紹介
2024.03.29
2023.06.15
「多様性」を意味する「ダイバーシティ」は近年、企業を経営する上で注目されているキーワードのひとつである。本記事では、ダイバーシティの意味や特徴、注目される背景、また取り組むことでもたらされるメリットやデメリットなどについても解説していく。

ダイバーシティの意味と特徴は?
企業経営をするうえで重視するべきことのひとつが、多様な人材を受け入れる取り組みだ。今回は、多様性を意味する「ダイバーシティ」について紹介する。近年ビジネスシーンでも注目が集まるワードのため、耳にしたことがある人も多いに違いない。まずは、ダイバーシティの意味と特徴について見ていこう。
ダイバーシティとは
ダイバーシティ(Diversity)とは、多様性を意味し、さまざまな属性の人が共存するという考え方を表す言葉である。1950年代以降、アメリカで盛り上がりを見せた公民権運動が契機となり、ダイバーシティの概念が注目されてきた。
アメリカにおいては1964年に公民権法が制定され、雇用の面でも属性にかかわらず公平であることが重視されるよう、社会全体の考え方が変わってきたのだ。ここでいう属性とは、次のようなものを指す。
・性別
・年齢
・人種
・国籍
・使用言語
・宗教
・学歴
・性指向
・障害の有無
・キャリア
・ライフスタイル
・働き方
・価値観
多様性を受け入れてそれぞれの個性と能力を活かし、労働市場で積極的に活用しようというのがダイバーシティの考え方だ。日本でもダイバーシティの概念は徐々に浸透してきている。少子高齢化による労働人口の減少という、日本社会が抱える課題に対しての解決策の一つとして、ダイバーシティが有効であると考えられているためだ。
ダイバーシティの分類
ダイバーシティは、「表層的ダイバーシティ」と「深層的ダイバーシティ」の2つに分類が可能である。
「表層的ダイバーシティ」とは、表層的な要素が影響し、外見で判断しやすい点を基準とした分類方法だ。これらの要素は主に自らの意思で変えることが難しい生まれ持った性質に基づくものであり、人種、国籍などが該当する。
一方の「深層的ダイバーシティ」は、外見ではわかりにくい要素によって決まることが多い分類である。深層的ダイバーシティは表面的にはわかりにくいため見落とされがちだが、実は重視すべき要素で、しばしば問題や論争の焦点となる。
それぞれが持つ多様性を許容することをベースとするダイバーシティという考え方では、これら両方の属性にある要素すべてを平等に重視し、企業内での戦力として活用していく方針をとる。
ダイバーシティとインクルージョンの違い
ビジネスにおいて、ダイバーシティと共に登場することが多い言葉に、「インクルージョン(inclusion)」がある。インクルージョンとは、「一体性」「包括」と訳され、もともとは「ソーシャルエクスクルージョン(社会的排除)」という概念を解決すべく登場した、「ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)」に基づく考え方である。
インクルージョンの概念はビジネスや教育領域で徐々に拡大し、認知度を高めつつある。ビジネスシーンでは、社員の内面的な特性が企業活動の中で十分に活かされている状態を指す言葉として使用されるのが一般的だ。
ダイバーシティとインクルージョンに共通するのは、個人を尊重しようという考え方である。このことからわかるように、体制面でダイバーシティを実現しているように見えても、インクルージョンが伴っていなければ、企業における真の人材活用と呼ぶことはできないのである。
ダイバーシティはなぜ注目される?

世界中で注目を集めるダイバーシティの考え方は、日本でも徐々に認知度を高めているのが現状だ。それでは、ダイバーシティはなぜ注目されているのだろうか。ダイバーシティが注目される背景と、国による施策について触れていく。
ダイバーシティが注目される背景
ダイバーシティが注目される背景には、いくつかの要因がある。まずは、企業のグローバル化だ。国内のみならず国外に進出するうえでは、国や地域を超えた考え方を理解して受け入れることが欠かせない。日本独自の考え方にこだわっていては、国際社会で競争力をつけることは難しいだろう。そのため、企業は多様な価値観を理解し、さまざまな属性の優秀な人材を積極的に採用し育成していく必要があるのだ。
また、日本国内の労働人口の低下も、ダイバーシティの推進を後押ししている。社会人として働くことが可能な人口を示す生産年齢人口は、2050年には現在よりもおよそ2,000万人以上も減少すると予測されている。今後、慢性的な人材不足となる日本では、ダイバーシティの考え方を許容して、国外からも幅広く優秀な人材を受け入れていくことが求められる。
さらに、仕事に対する意識や価値観の変化や消費行動の多様化もダイバーシティと親和性が高い。ワークライフバランスを重視し、仕事にやりがいを求める人材が増えたことで、企業側も意識の変革を迫られているといえるだろう。個人の消費に対する意味付けが、「コト消費」重視に遷移しているトレンドなども、ダイバーシティの推進を後押ししている要因の一つであると考えられる。
国による施策
日本国内におけるダイバーシティ関連の取り組みは数多いが、なかでも注目すべきなのは、国が主導している施策である。
経済産業省が推進する「ダイバーシティ2.0」という取り組みでは、行動ガイドラインを制定し、企業経営においてダイバーシティの導入と促進を目指している。女性や外国人、若者、高齢者の雇用や登用促進などを中心とした施策に注目が集まる。それぞれの属性における人材活用の指針となるべきガイドラインとなっているので、企業がダイバーシティを導入・推進するうえで活用が見込まれる。
また、厚生労働省でもダイバーシティ推進の施策を実施している。「働き方改革」の一環として提唱された取り組みで、女性の社会進出の支援を中心として子育て支援関連の推進にも積極的である。あわせて、企業への認定制度や法整備も並行して進めているため、よりダイバーシティが浸透しやすい社会となることが期待されている。
ダイバーシティの導入方法
自社にダイバーシティを導入したいと考えたとき、どのような手順で進めるべきか迷うことがあるかもしれない。その際には、経済産業省によるダイバーシティ導入の手引き書の「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン」が役立つであろう。ガイドラインによると、ダイバーシティ経営の実践手順としては、以下のように明記されている。
1 経営戦略への組み込み
2 推進体制構築
3 ガバナンス改革
4 全社的環境、ルール整備
5 管理職の行動と意識改革
6 従業員の行動と意識改革
7 労働市場、資本市場への情報開示と対話
ダイバーシティの導入では、トップダウンで段階的に施策導入を推進していくことが有情である。また、体制だけではなく、意識改革も欠かせない。社内だけではなく自社のダイバーシティに関する取り組みを社外に対しても情報公開していくことで、より開かれた企業であるという意識付けも可能となる。
経済産業省では、自社へのダイバーシティ導入の可視化に役立つ「改訂版ダイバーシティ経営診断ツール」を無償提供しているので、ぜひ活用したいものである。
ダイバーシティのもたらす効果、メリット・デメリットとは?

導入にはメリットが多そうなダイバーシティであるが、実際のところはどうなのだろうか。ダイバーシティを導入する場合、導入のメリットとデメリットの両面から、事前に把握しておくことが欠かせない。ここでは、自社において実際にダイバーシティ経営を開始したときに考えられる、効果と考慮すべき点を見ていこう。
ダイバーシティ導入のメリット
ダイバーシティを正しく導入し、企業文化として根付かせることは容易なことではないが、うまくダイバーシティを取り入れることができれば、以下のようなメリットの享受が期待できる。
イノベーションの促進
様々な経験と視点を持つチームメンバーは、新しいアイデアやソリューションを生み出す可能性が高まる。多様性があることで、問題解決のアプローチが多角的になり、新たな企画やアイデアの創出が可能になり、同質的な人材だけの組織と比べてよりイノベーションが促進されやすくなるといった効果が期待できる。
市場への理解の促進
多様な社員を持つ企業は、グローバルな市場や多様な顧客層のニーズをより深く理解し、ターゲット市場に効果的にアプローチできるようになる。海外進出にあっては現地の消費者のマインドや文化を深く理解する必要性が発生しやすい、自社製品のことも理解し、さらに現地の文化への造詣が深い人材がいれば、市場参入において大きなアドバンテージとなりうるだろう。
ブランドイメージの向上・従業員満足度の向上
ダイバーシティに積極的な企業は、社会的に責任ある組織と見られる傾向がある。これは顧客や投資家からの好意的な認識を生み出し、企業イメージの向上につながり得る。
企業イメージの向上は、所属する従業員のモチベーションや満足度にもつながりうる。また、純粋に、ダイバーシティを重視する文化では、互いを尊重し合える包括的な職場環境を創出されやすくなり、社員間のコラボレーションを促し、チームワークを強化、リテンションの強化といった効果も期待できる。
多様で優秀な人材の確保
ダイバーシティを導入することで、 利用できる人材プールが広がるため、優れたスキルと才能を持つ候補者を獲得する機会が拡大する。
そのため、さまざまなバックボーンを持つ優秀な人材が集結しやすくなる。この際、社員の定着率アップにつながる施策もあわせて実施することが欠かせない。リモートワークの容認など、よりワークライフバランスの向上につながる施策も併用すべきといえる。
ダイバーシティ導入のデメリット
ダイバーシティ導入には、いくつもの魅力的な効果があるが、残念ながら導入に伴うデメリットもあるのが現実である。ダイバーシティ経営においては、経営トップだけではなく、全社における意識改革が欠かせない。
意識改革が十分でなかった場合に想定される事態として、価値観の相違によるハラスメントや従業員同士の衝突が予測される。
また、ダイバーシティ経営が全社に浸透していないケースでは、公平性に疑問を持つ社員が出る可能性もあるだろう。これらは結果的に、生産性や企業体力の低下に直結するため、看過できない問題となるのだ。
そのため、ダイバーシティを推進する場合には、言語の相違によるコミュニケーションの不足を補い、社員同士がお互いに尊重し合える環境を企業側が十分に整備してから体制変更をスタートすることが求められる。
また仮に徐々に改革を行う場合であれば、要所ごとにトップダウンの意思決定を明確に伝達し、全社で認識の齟齬が発生しないように推進していきたいものだ。
企業におけるダイバーシティの取り組み事例
以下では、ダイバーシティに取り組む国内先進企業の事例を紹介していく。
資生堂
資生堂では、「LOVE THE DIFFERENCES(違いを愛そう)」というスローガンのもと、お互いの違いを認め尊重し合うために、ダイバーシティを導入している。ジェンダー平等推進のため、女性の登用と女性リーダーの育成に積極的である。
また2017年からは、社員の同性パートナー異性配偶者と同等に処遇するという画期的な取り組みも開始している。そのほか、障がい者雇用や海外現地法人での外国人の採用、希望者に対する再雇用制度などにおいても積極的に取り組んでいる。
イオン
イオンは、国内外で300を超える企業が集まるグループ企業である。もともと多彩な人材が集まる環境にあるため、ダイバーシティ経営を推進することが非常に効果的な環境といえる。「日本一女性が働きやすく活躍できる会社」と「女性管理者比率50%」を目指して取り組みを行っており、すでに女性管理職は9,000人を超えている。また、LGBTQ +に関する研修を実施し、全社員に対する意識付けも推進している。
セブン& アイホールディングス
セブン& アイホールディングスでは、多様な人材が意欲を持って能力を発揮できることを目標に、職場環境の整備に努めている。ジェンダー平等を目的とした女性執行役員と女性管理職の比率を30%以上にアップするための施策や、男性従業員への育児参加の推進、介護離職者ゼロなどが主な取り組みである。また、障がいがある社員への職場定着支援にも積極的だ。
ファミリーマート
ファミリーマートでは、ダイバーシティを重要な経営戦略として確実に推進するため、経営陣で構成し、社長が委員長を務める「ダイバーシティ推進委員会※」のもと、ダイバーシティ推進グループが中心となって戦略的に取り組んでる。
ダイバーシティ推進委員会は、社長が委員長、経営陣でメンバー構成される委員会。企業価値向上のために多様性を活かした組織風土の実現に向けたKPIを設定し、KPIマネジメントを実施している。
また、、2026 年 2 月末までの目標を設定、女性管理職比率:10%、離職率における男女差:0.5%以内など、女性の活躍に関する目標を設定。
管理職候補の女性社員を対象に外部開催の異業種合同研修への派遣を実施するなどの「女性育成研修プラン、女性活躍推進のための女性社員による「自分たち自身の成長と変革」「ネットワーキング」「会社の成長と変革」を目的としたボトムアップ活動「FamilyMart Women Project(FMWP)」を実施している。
おわりに
ダイバーシティ経営は、グローバル化が進んできている現代においては、各企業が優先的に取り組むべき施策である。自社でダイバーシティ経営を導入・推進する場合には、政府指導の方針に基づいて進めるのがおすすめだ。社内全体にダイバーシティの考え方をしっかりと浸透させ、効果的なダイバーシティ経営の導入を推進することで、より魅力的な企業経営に活かしていきたいものだ。