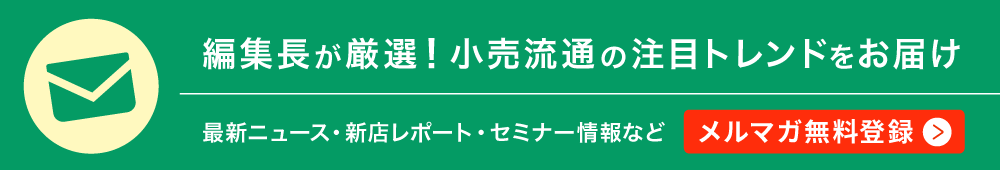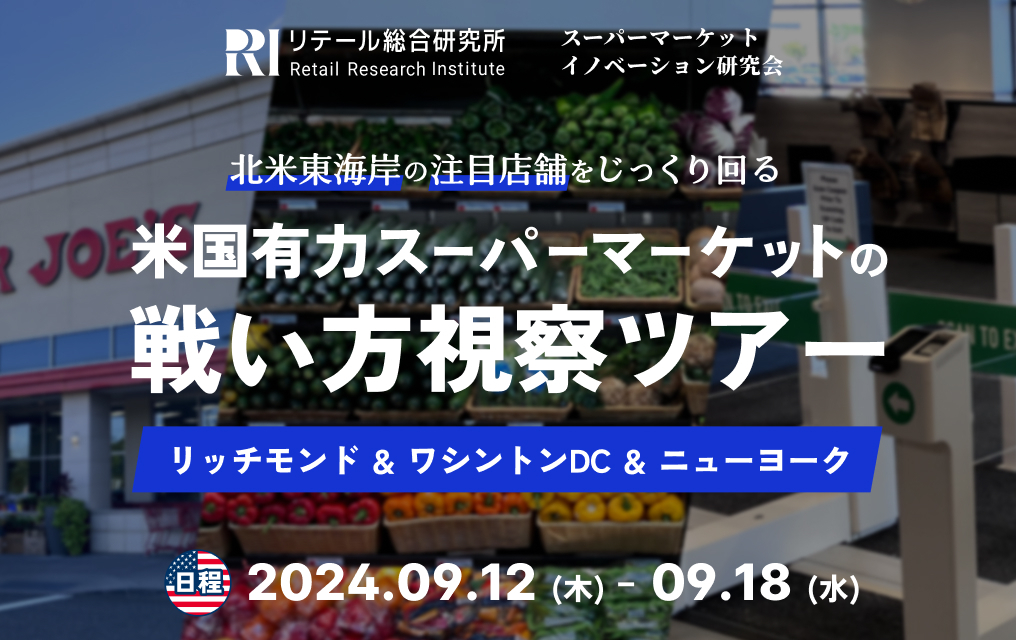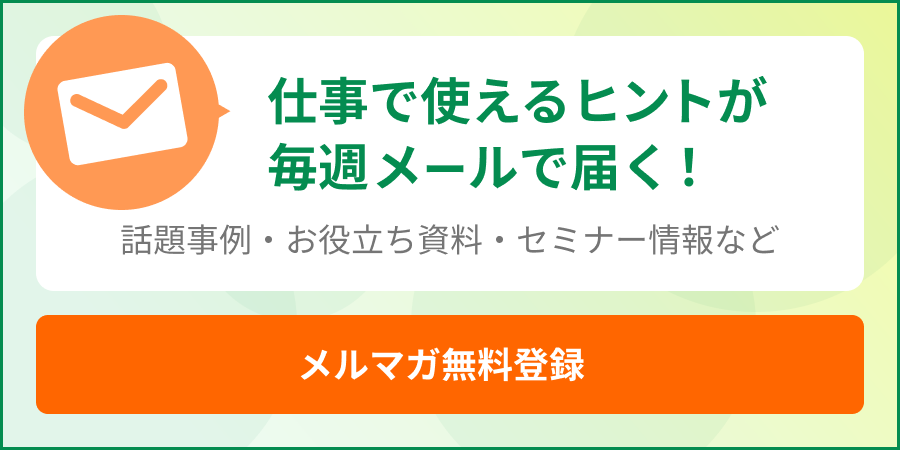「2025年の崖」とは?政府がDX化を推進する背景にある課題等を解説
2022.10.27
2022.01.11

DX推進の問題は民間だけではなく、政府も専門家会議を設けるなどして日本企業のDX化を強く推進している。政府がDXを推進する背景には、「2025年の崖」と呼ばれる大きな経済損失を伴うリスクが存在している。
今回は、この2025年の崖とはどのようなもので、どんな背景から、どの程度の損失が出るのかを確認していく。
2025年の崖とは?
2025年の崖とは、経産省が2018年に『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』(DXレポート)というレポートの中で提唱したものだ。
長年の使用に伴い、複雑化、老朽化、ブラックボックス化したシステムが問題となっているが、これらのシステムを使い続けることにより、現在の約3倍となる12兆円の経済損失が発生するといわれている。
12兆円の経済損失を軽減、回避するためには、既存システムを刷新し、最新のデジタル技術やデータを活用できる環境を整えていく必要がある。
「2025年の崖」において生じる損失とは?

既存システムの残存により、2025年以降に12兆円の経済損失を被る可能性があることは前節でも述べたが、具体的に企業側でどのようなデメリットが生じるのか。
ここからは、ユーザー企業側に発生する3つのデメリットについて詳しく解説する。
データを活用できずにデジタル競争の敗者に
DXの成功には、最新のデジタル技術とデータの有効活用が求められるが、経済産業省のDXレポートによれば、既存のシステムのままではデータの有効活用ができず、デジタル競争の敗者となるリスクを指摘している。
これまでわが国で構築されてきたシステムは、会社の事業部門などのように個別最適化を重視した構築がなされ、そのため、情報資産やデータを数多く保有していたとしても、会社全体での情報管理やデータ管理の連携が難しいとされている。
全社間での情報連携が難しい現在の状況では、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、ビッグデータをはじめとする最先端テクノロジーを導入したとしても、その効果が限定的になするリスクがある。
データを最大限活用するためには、既存システムの改変、刷新し、柔軟にデータの連携、活用ができるシステムを構築する必要がある。しかし、システムの構築から長い年月が経過しているシステムは、度重なる修正や変更に伴うプログラムの複雑化が想定される。
プログラムの複雑化だけでなく、マニュアルの整備が不十分であったり、エンジニアの定年などでシステムに精通した人材が不足したりする事態も考えられるだろう。
来る2025年に備え、既存システムの課題や問題点を理解し、それに向けた対策を講じることが重要となる。
システム維持管理費が高額化する
第二に、既存システムを維持する管理費の高額化が指摘されている。
わが国の企業において、システムの維持管理費は、支出の多くを占める重要な要素である。
事実、JUASの「企業業IT 動向調査報告書 2017」によると、IT関連費用の80%以上が、既存システムの運用、保守に充てられているという。
加えて、既存システムの維持管理費は、増加傾向にある。
システムに使用されているソフトウエアのサービス終了や、システムを理解したエンジニアの定年による退職などが要因として挙げられる。
また、プログラミング言語の多様化も、システム維持管理費の高額化の一因だろう。プログラミング言語の多様化に伴い、開発時に使われていた言語を扱える人材が減少・不足し、希少価値が高くなるためだ。
特に既存システムは、古い機器や古い部品を使われていることも多く、システムの故障や不具合が生じる可能性も高い。
各企業で既存のシステムの改修や刷新をいかにして進めるか、そのプランニングが問われる。
システムトラブル、データ滅失などのリスクが高まる
第三に、システムトラブルやデータ滅失をはじめとした、セキュリティリスクの高まりが懸念される。
特にセキュリティは、システムダウンにも大きく直結するなど、経営活動を進める中で非常に重要な要素だ。
システムトラブルやデータ滅失のリスクが高まる要因の一つとして、既存システムのサービス、製品のサポート終了やサービスの切り替えが挙げられる。
最近では、Microsoft社の「Windows7」のサポート終了が記憶に新しい。
Windows7のサポートが終了した20年1月14日以降は、当然だがセキュリティの更新プログラムが提供されなくなっている。
セキュリティの更新プログラムが提供されなくなることにより、Microsoft社はWindows7に対するマルウエアへの感染やフィッシング詐欺をはじめとする、セキュリティリスクの警鐘を鳴らしている。
Microsoft社のWindows7以外にもこの先、NTT東日本による固定電話の設備切り替えが2024年1月に、SAP社のERP製品の2027年限りでのサポート終了が判明している。
これらのサービス、製品のサポート終了などに伴うセキュリティリスクを回避するための、方針や対策が求められる。
「2025年の崖」の生じる背景にある問題

2025年の崖によって生じる損失を軽減、回避するためには、DXの推進が欠かせない半面、日本全体でみると、企業は幾つかの問題を抱えている。
そこで、ここからはDXの実行を阻害する問題、課題について詳しく解説する。
IT人材の不足
1つ目の問題として、IT人材の不足が挙げられる。
中でも特に、ユーザー企業の人材不足が著しい。
ユーザー企業のITエンジニアの人材不足に加え、ITエンジニアの7割以上がベンダー企業に偏在している事実もあり、わが国のシステム開発はベンダー企業頼みとなっている。
一方、海外の企業に目を向けると、自社内にITエンジニアを抱え、開発を主導して行うケースも少なくない。
自社内にITエンジニアを抱えていることにより、システムに関するノウハウの共有も容易であり、定期的にメンテナンス作業を実施すれば、システムのブラックボックス化などは起きにくいものだ。
しかし、ベンダー企業頼みの傾向が強いといわれるわが国の場合、自社内にITシステムに関するノウハウが残ることなく、ベンダー企業側にノウハウが溜まるという問題を抱える。
その結果、システムの複雑化やブラックボックス化などが進んでいるのが現状だ。
また、ユーザー企業のIT人材の不足による影響は、ITエンジニアの偏在だけにとどまらない。
長年、ITシステムの開発、運用に携わってきた有識者の定年退職も課題となっている。
有識者が持つノウハウがドキュメントなど「で整備されていなければ、有識者の退職により既存システムのノウハウが喪失され、ブラックボックス化などが進むこととなる。
有識者の退職に備え、ドキュメントなどの整備を行い、いかにして社内でノウハウを管理、共有できるようにするか、その仕組み作りが求められる。
ベンダー企業への依存状態
2つ目の問題として、一部のユーザー企業では、必要とする要件を明確化することなく、要件定義の段階から全てベンダー企業に任せすぎてしまう点だ。
要件定義の段階からベンダー企業に任せてしまっているため、ユーザー企業は、既存システムの肥大化、複雑化やシステムの仕様について理解できていない場合がある。
ユーザー企業がシステムの全容を理解できていない中、ベンダー企業に業務委託をするため、作成されたシステムはユーザー企業の意図と異なるシステムが完成されることは少なくない。
作業工程の手戻りが生じ、開発費用が膨れ上がるだけでなく、システムの完成が当初の予定より遅れることで機会損失が発生する場合もある。
特に近年は、ユーザー企業とベンダー企業間での意図の食い違いから訴訟へ発展するケースの増加も指摘されている。
技術的負債には気付きにくい
3つ目の問題として、ユーザー企業は既存のシステムが抱えるシステムの複雑化やブラックボックス化などに対処しにくいという問題がある。
これらのシステムの複雑化やブラックボックス化なども、従来からのベンダー企業への依存状態が大きく関係している。
仮に、システムの複雑化やブラックボックス化など、いわゆるレガシー問題を自覚していた場合でも、システムの刷新を決行するには、長期間かつ莫大なコストが発生し得る。
この観点からも、既存のシステムが稼働している間は、システムの複雑化やブラックボックス化などには対処しにくいだろう。
既存システムに故障や不具合が生じて、そこで初めて問題が浮き彫りになるものだ。
故障や不具合が生じなかったとしても、既存のレガシーシステムを短期的な観点で開発し、長期間にわたり、運用費や保守費を支払い続けているケースも少なくない。
こうした短期的な観点で開発されたシステムに支払う運用費や保守費は、負債ともとらえることができ「技術的負債」(Technical Debt)とも呼ばれる。
ちなみに、ここでいう短期的な観点での開発とは、時間やコストなどの制約により本来備え付けるべき機能を取り込めず、必要最低限の機能しか取り込めていないことをいう。
既存システムの運用費や保守費の支払いが長きにわたり支払われることにより、DXを実行するために必要なリソースが圧迫されてしまう。。
このように技術的負債は、DXの推進を阻害するリスクとなるため、経営者には技術的負債の重要さを認識することが求められる。
「2025年の崖」のまとめ
これまで「2025年の崖」について、2025年の崖によって生じる企業のデメリットや、DX化を推進する際に生じる具体的な問題点や課題について述べてきた。
DX化を推進するにあたり、レガシーシステムからの脱却や人材不足など問題状況だが、2025年のタイムリミットは刻一刻と迫っている。
各企業には、デジタル競争に追随するためにも、着実に課題を解決していき、他国の企業に遅れることなくDXを推進する必要があるだろう。