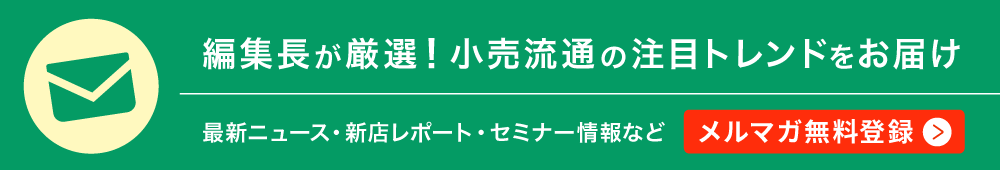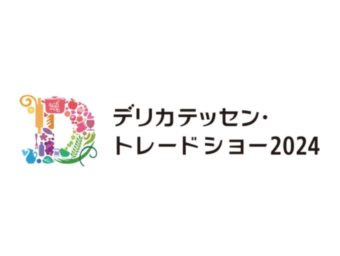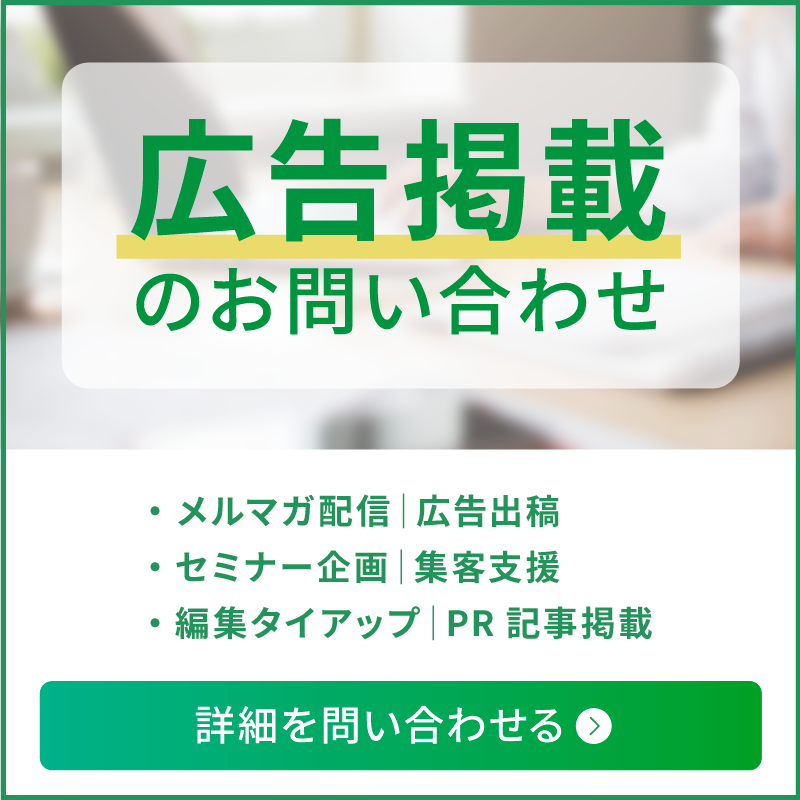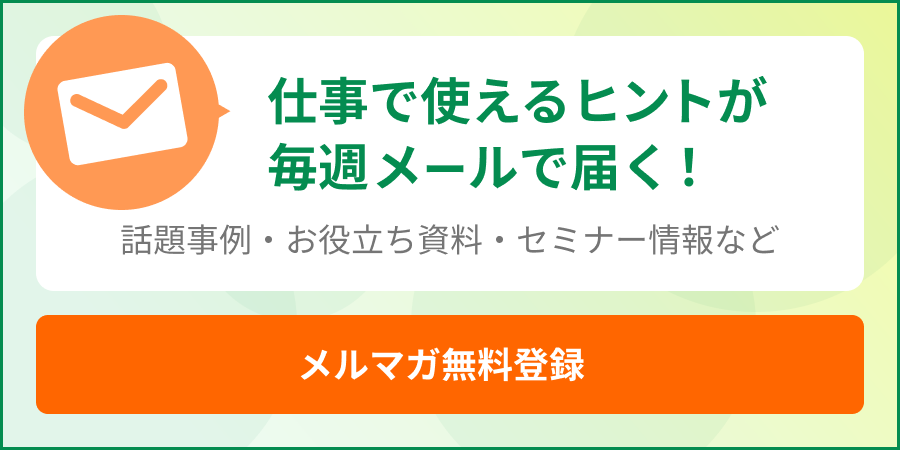α世代とは?年代や価値観、消費行動の特徴を、その他世代などの違いと併せて解説
2023.05.12

昨今ではZ世代やミレニアム世代といった世代分けの概念が、マスコミ業界やマーケティング業界など、さまざまな業界で多く用いられている。その中でも、Z世代よりも若い世代を指し、価値観や消費行動など今後の動向に注目が集まっているのが、α世代(アルファ世代)だ。
本記事では、α世代の基本から対象年齢、特徴、他の世代との違いまで解説していく。
α世代とは?対象年齢は?
α世代とは、2010~2024年頃(平成22年~令和6年頃)に生まれた世代を指す用語で、「ジェネレーションα」と称されることもある。2023年時点における対象年齢は13歳以下であり、最年長で中学1年生となっている。
α世代の多くは、1980~1995年の間に誕生した世代「ミレニアル世代」の子供で、幼少期からスマホやタブレットにも親しみが深い。学校の授業ではタブレットも積極的に導入されており、またプログラミングの必修化も影響し、幼少期におけるデジタル機器の接触機会は比較的多いデジタルネイティブ世代と言えるだろう。
その他、Withコロナの生活様式が染み付いているのも、α世代の大きな特徴。私生活・園生活・学校生活をコロナ禍で送ってきており、デジタルネイティブも相まって、オンラインに対する抵抗も少ないと考えられる。
α世代の由来
α世代の概念は2005年に、オーストラリアの社会学者であるマーク・マクリンドル氏によって提唱された。これまでX世代・Y世代・Z世代と、さまざまな世代が定義されているが、α世代はZ世代に次ぐ新たな世代となる。
なお、ラテン文字の最後に当たる「Z」がZ世代で使用されたため、α世代にはギリシャ文字の最初に当たる「α」が採用された。
α世代の人口数
総務省が2022年4月15日に発表した、2021年10月1日時点における人口推計によると、α世代の年齢別人口数は下記のようになっている。
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
| 0歳 | 425 | 405 | 830 |
| 1歳 | 427 | 408 | 836 |
| 2歳 | 446 | 425 | 871 |
| 3歳 | 468 | 446 | 915 |
| 4歳 | 480 | 458 | 938 |
| 5歳 | 502 | 477 | 978 |
| 6歳 | 514 | 489 | 1,003 |
| 7歳 | 514 | 488 | 1,001 |
| 8歳 | 525 | 501 | 1,026 |
| 9歳 | 527 | 503 | 1,029 |
| 10歳 | 540 | 514 | 1,054 |
| 11歳 | 545 | 518 | 1,063 |
| 合計 | 5,913 | 5,631 | 11,544 |
※単位:千人
日本の総人口は1億2550万人と推計されているので、2021年10月1日時点におけるα世代の割合は約9.2%となる。
マーク・マクリンドル氏は世界人口の増加に伴い、2025年にはα世代が歴史上最大の世代になると述べている。世界的に注目されるα世代だが、出生率の低下が進む日本では、他の年代に比べて人口比率が低い。
現在の消費行動に関しては基本的に親が介入しており、購買力は決して高いと言えないが、将来は中心的な消費者となってくる。人口比率こそ低いものの、今から消費行動や価値観を分析し、今後のマーケティング活動に活かしていくことが重要と考えられるだろう。
α世代の価値観や消費行動の特徴
ここでは、α世代が持つ価値観や消費行動の特徴を考察していく。
優れたデジタルリテラシーを有している
α世代の大きな特徴として挙げられるのが、デジタルリテラシーの高さ。昨今のデジタル技術の進化は凄まじく、教育現場においてもICT技術は活用されている。
例えば、デジタル教材を活用すれば、生徒は自らの疑問を深く探求でき、自身に最適な進度で学習が可能となる。教員に関しても、電子黒板などを利用して音声・動画を流し、授業の効率化・高度化を図るケースも多い。
ICT教育の推進は生徒の学習意欲を向上させるだけでなく、さまざまなデジタル機器に触れていく中で、必然的にデジタルリテラシーも高めていく。また、生徒のIT分野への興味関心を引き、ITに関する知識の吸収促進も期待できる。
さらに、α世代の親の中心が、高度なデジタルリテラシーを持つミレニアル世代であることもポイント。インターネット上のリスクや各種デバイス・ツールの使い方、検索方法なども親から学ぶことが可能なので、デジタルリテラシーも身に付きやすい環境が揃っていると言えるだろう。
バーチャル空間に好意的
α世代はリアルとバーチャル空間の隔たりを持たず、バーチャル空間に好意的な世代とも言われている。
Withコロナ時代を過ごしてきたα世代だが、コロナ禍を契機として広く活用されるようになったのが、VR・AR・メタバースなどのバーチャル技術。VRヘッドマウントディスプレイを使用せずとも、スマホゲームやイベントの場などで仮想現実・拡張現実を楽しめるため、バーチャル空間がより身近な存在に。
また、学校でもメタバースを活用した国際交流、不登校児童向けのメタバース登校といった、バーチャル技術を活用したさまざまな取り組みが行われている。現実世界に限らず、バーチャル空間における生活の在り方や楽しみ方なども理解しており、先進的な技術への適応力も非常に高い。
自ら消費行動を取る年齢になった際も、メタバースECやバーチャルショップといった先進技術でアプローチしていくことは有効と考えられるだろう。
オンライン上の交流に抵抗がない
バーチャル空間に好意的なα世代は、オンライン上における交流にも抵抗を示さない。
コロナ禍では外出自粛が呼びかけられていたが、一方でコミュニケーションツールが数多く開発・リリースされ、幅広く認知されるように。SNSやオンラインゲームをはじめ、VR・メタバース上にアバターを作成し、友人だけでなく全世界の人々と交流することも可能となった。
オンラインコミュニケーションは双方の意図や感情が伝わりにくく、ツールに強い抵抗感を持つ人も多い。しかし、α世代はオンラインコミュニケーションツールの重要性・必要性を心得ており、今後も強い関心を示すだろう。
タイムパフォーマンスを意識する
タイムパフォーマンスとは、かけた時間に対する成果や満足度を指す用語で、α世代はタイムパフォーマンスを重視する傾向にある。その一例として挙げられるのが情報収集だ。
昨今ではオンライン・オフラインを問わず、さまざまな手段で情報の収集を行えるが、テレビ・新聞・書籍といった媒体は情報の検索に一定の時間を要する。その点、α世代はWebサイトやSNSなどを活用し、欲しい情報を手早く入手する傾向に。
短い時間で最大限の成果を得ることを、α世代は意識していると言えるだろう。
人々の多様性を尊重する
α世代は価値観・性別・ライフスタイル・恋愛観など、人々の多様性を尊重する傾向にある。
前述の通り、α世代はオンライン上における交流が活発で、見ず知らずの人と接する機会も少なくない。さまざまな人種・性別・思想に触れていく中で、自身の考えだけに固執せず、他人の多様性も認めていくと考えられる。
日本では働き方の多様化や女性が活躍する環境の推進など、ビジネス面においてもダイバーシティの考え方が注目を集めており、またLGBTを巡る動きも活発化している。このような日本の考え方にも、α世代は高い順応性で対応していくと想定できるだろう。
Z世代などその他世代との違い
世代分けの概念はα世代以外にも、下記のような区分が存在する。
| 生まれ年 | 年齢(2023年現在) | 日本名別 | アルファベット・ギリシャ文字別 |
| 1965~1969年 | 54~58歳 | バブル世代 | X世代 |
| 1970~1974年 | 49~53歳 | 団塊ジュニア世代 | X世代 |
| 1970~1982年 | 41~53歳 | ロスジェネ世代 | X世代・Y世代 |
| 1980~1995年 | 28~43歳 | ミレニアル世代 | Y世代 |
| 1987~2004年 | 19~36歳 | ゆとり世代 | Y世代・Z世代 |
| 2010~2024年 | 0~13歳 | ー | α世代 |
上記の中でも注目したいのが、α世代と年齢が近いZ世代。Z世代とは、1990年代後半~2012年頃に誕生した世代を指し、2023年時点では10代前半から20代後半の人が該当。α世代と同様、Z世代もダイバーシティな考え方を持ち、またインターネット環境も当たり前に存在していた。
共通する部分も多いα世代とZ世代だが、α世代はZ世代を超えるデジタルネイティブ世代とも言われている。Z世代は成長していく過程で、スマホ・SNS・キャッシュレス決済・バーチャル空間などのデジタル技術・サービスが大きく普及していったが、α世代が育つ頃には現在の先進技術は概ね一般化。
先述の通り、学校教育でも先進技術は活用されており、プログラミング教育に関しては早ければ幼稚園から導入されている。幼少期からさまざまな先進技術に接しているα世代は、Z世代よりもデジタルネイティブと言えるだろう。
また、α世代が成長する頃にはTwitter・Instagram・TikTok・YouTubeなど、さまざまなSNSが広く認知されるように。小さい頃から自身の意見を述べることができ、自己主張に対する抵抗感がZ世代より低いと想定されている。上手くSNSと向き合っていけば、自己主張スキルの向上にもつながると考えられるだろう。
α世代のまとめ
α世代は最年長が中学生となっており、実際の価値観はまだまだ不明瞭な部分が多い。消費行動に関しても、現在は自身が主体ではないため、将来の行動を予測することが重要。
とは言っても、親のミレニアル世代の価値観や消費行動は、少なからず子のα世代にも反映されると予想できる。α世代にマーケティングを行う際は、親がミレニアル世代であることと、α世代が育ってきた環境を考慮しながら施策を立案したい。