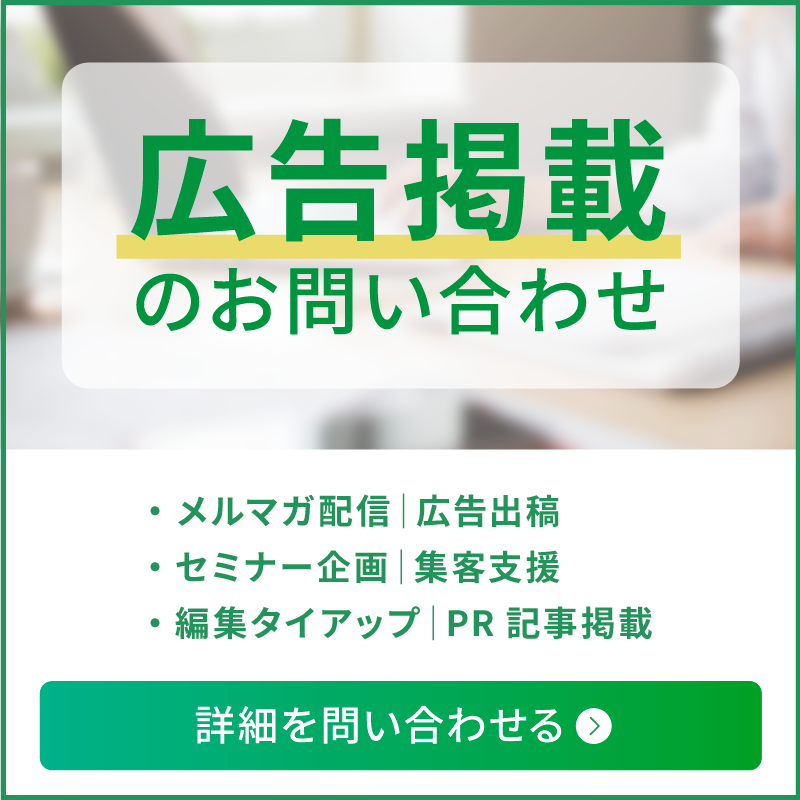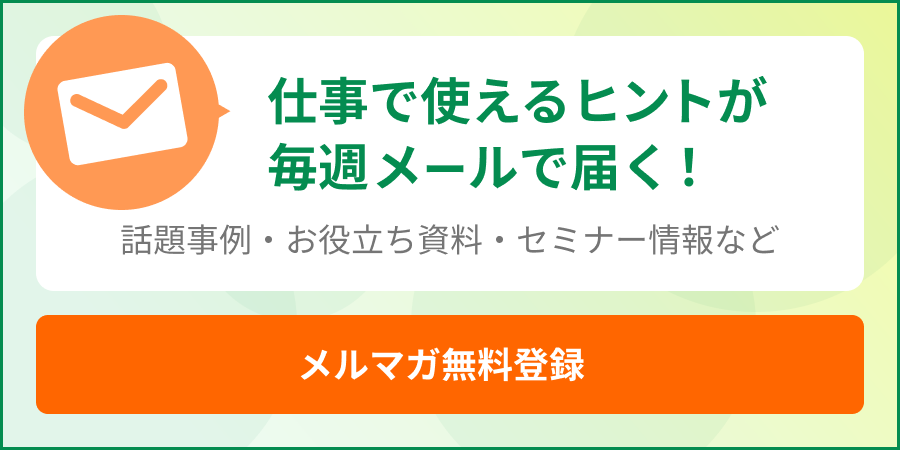- 連載:
- 食のトレンドウオッチ!
第1回 ぐるっと回ってたどり着いた先に「ニッポン」
2022.11.09
2022.03.25
今月よりコラムを連載する。私は世界の食品トレンドを日本に伝えて、企業の商品開発やマーケティング活動、また海外展開を支援している。そのため、もちろん、執筆内容は「世界の食」が中心になるが、私が普段仕事を通して感じていることを、番外編的にゆるりと書いていこうと思う。

「へー、こんな意見もあるんだ」くらいに気楽に読んでほしい。ゆるくもあり、真髄に迫っているって言われると、ちょっぴりうれしいかもしない。
一般的に世界、特に欧米の食品トレンドは「進んで」おり、それが数年遅れで日本に入ってくると言われている。あらゆる国の食品を幅広く見ている私の実感としても、確かにそのとおりではあるが、実は日本が昔から最先端を走っている分野もそれなりにあると感じる。しかも多くの場合、そのことに日本人が気付いていないから、なんとも奥ゆかしい。
私と同期入社で、いまや当社のトップアナリストに上り詰めたフランス人(オランダ在住)の女性が、グローバル規模のセミナーでこんなことを言っていた。
「植物性ミルクの搾りかすをアップサイクルする取り組みがはじまっています。プラントベースの搾りかすは予想以上に栄養満点で、これを植物性のお肉に混ぜ込んだり、パウダー状にしてベーカリーに活用したりなど、サステナブルの観点からも注目されはじめているんですよ。その名をOKARAと言います」

「え、 おから?」 それって日本人が伝統的に、普通に食べてきたものじゃないか。何をいまさら…。欧米諸国の最先端の食を取り扱っている人たちが目を付けはじめたって? しかもサステナブル、プラントベース、アップサイクルなど、現代のかっこいいトレンドキーワードを織り交ぜて語られると、「おから」がまるでスーパーサイヤ人になったような印象を持ってしまい、心の中でくすっと笑ってしまった。
自分の中で、もやもやしていた伝統食とイノベーションの兼ね合いというかジレンマの混沌が、にわかにひも解けた瞬間だ。
このように、先頭を突っ走っている欧米諸国が紆余曲折して、最終的に 日本的な考え方に落ち着くことがしばしばある。どうやらYes/Noがはっきりしないとやゆされる日本人は、人間にとって、あいまいかつ程よい着地点を長い歴史の中で見いだしてきているようなのだ。その一事例が「OKARA」の名を借りて、現代のグローバル社会の中で表面化したのかもしれない。
しかし日本国内しか見ていない人は、この壮大なる事実に気が付きにくい。やはり外の視点を持つことは、自分たちを見直すことにつながるのだろう。
似たような事例は他にもある。海外の食品関係者に、日本のサステナブル事例を聞かれたので、酒粕について熱く語ってみた。理由は単に私が日本酒が大好きだからだ。並行複発酵で醸す日本酒の製法は、世界の中で唯一無二であると同時に、その搾りかすである酒粕は、奈良漬に活用されるなど食材として非常に優れている。日本酒にはむだがないのだ、と伝えたら、その人は「Impressive!(素晴らしい)」と驚嘆していた。日本酒文化が誇らしくなった。
探せばこのような事例はたくさんあるはずだ。欧米諸国があれこれイノベーティブな道を進み、ぐるっと一周回って最終地点は、伝統的な日本トレンドにたどり着く。そんな視点で日本をじっくり見てみると、周回遅れだと思っていたことが、実はずっと先を走っていたなんてことがある。これからの時代を生き抜くヒントが見えてくるはずだ。
できれば日本人が先回りをして、さまざまな国の人たちに、最終地点となりうる日本の伝統食をやさしく教えてあげることができれば、世界からも喜ばれる。グルグル回りすぎて迷走しないように気を付けたい。