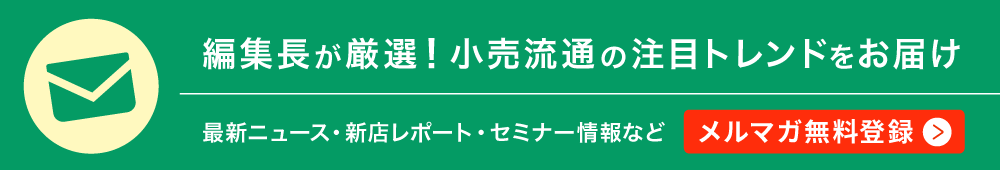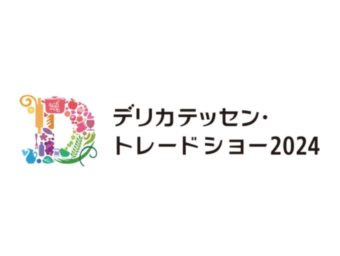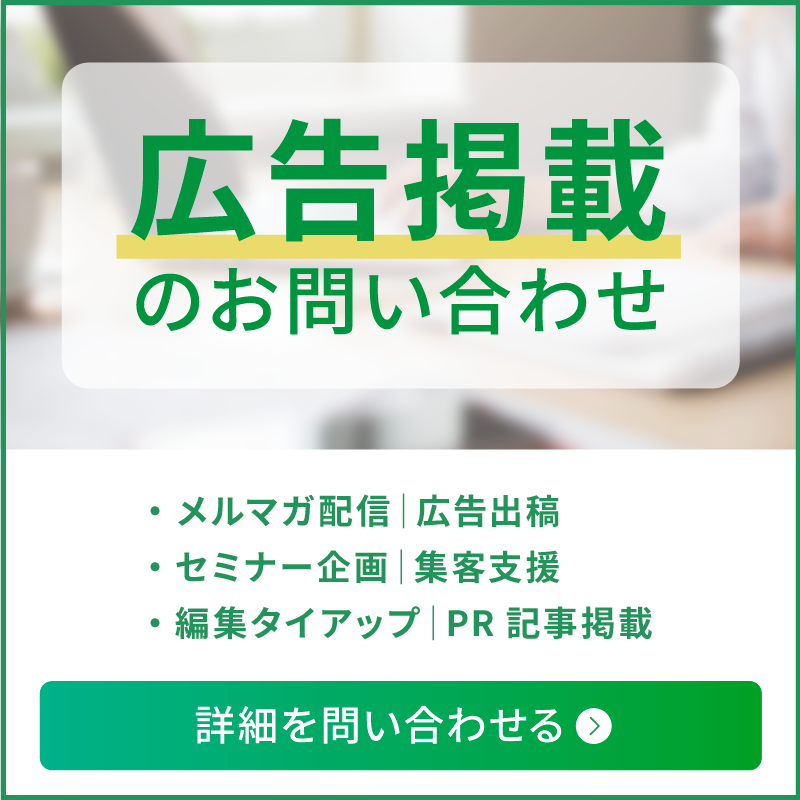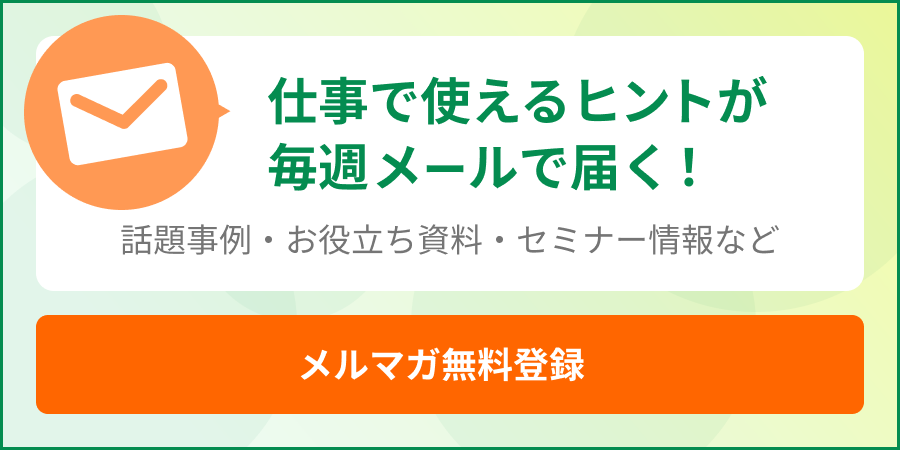SX(サステナビリティトランスフォーメーション)とは?意味や求められる背景、DXとの違いなどを解説
2024.03.26
2022.08.25

昨今、デジタルイノベーション・環境問題・新型コロナウイルスの感染拡大などが影響し、社会やビジネスの先行きが不透明となっている。将来の予測立てが困難な時代では、企業の稼ぐ力を強化して、サステナビリティを高めていくことが重要。
そのような中、経済産業省が各事業者に推進しているのがSX(サステナビリティトランスフォーメーション)だ。本記事では、SXの詳細から求められる背景、DXとの違いまで解説していく。
SX(サステナビリティトランスフォーメーション)とは?
SX(サステナビリティトランスフォーメーション)とは、企業が自社の強み・競争優位性・ビジネスモデルなど稼ぐ力の強化と、ESG(環境・社会・ガバナンス)を両立する、持続可能性を重視した経営方針を目指す概念である。
経済産業省は2014年8月、日本企業が世界有数のイノベーション創造力を保有していながら、持続的低収益に留まり、なおかつイノベーションへの投資規模が縮小して低収益性が持続する悪循環に陥っているとして、「伊藤レポート」を公表した。
本レポートでは、このような日本の現状を打破すべく、中長期的に企業価値を向上するために内部留保の戦略的配分や、企業の成長に関する投資の在り方について、投資家と建設的な対話を進めることが重要であると提言された。
さらに、2017年には「伊藤レポート 2.0」を公表。内部留保をイノベーションの源泉となる人材・知的財産・ブランドなど無形資産に投資することの必要性や、環境・社会・企業統治にも配慮したESG投資を積極的に推進すべきと指摘した。
また、経済産業省は「DX推進ガイドライン」や「CGSガイドライン」などを策定し、企業と投資家の対話を後押し。さらに2019年11月には「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」を設置。企業と投資家の対話を一層推し進めるため、SXを提示し、問題解決の方向性を提言した。2020年8月に「中間取りまとめ」としてサポートが出されている。
SX(サステナビリティトランスフォーメーション)が求められる背景
持続可能性を重視した経営方針への転換は、企業の積極的な投資が重要とされているが、資本の投入先として投資家から理解を得られにくいテーマも存在する。経済産業省は具体的なテーマとして、下記を挙げた。
- 多角化経営やそれに伴う複数事業のポートフォリオ・マネジメントの在り方
- 新規事業創出やイノベーションに対する「種植え」に関する取組
- ESG/SDGsなどの社会的価値と企業の稼ぐ力・競争優位性に基づく経済的価値の両立に向けた取組
各テーマからSXが求められる背景を解説していく。
多角化経営やそれに伴う複数事業のポートフォリオ・マネジメントの在り方
昨今のデジタルイノベーションや新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、社会・ビジネスは先行きが不透明になりつつある。
中長期的な環境変化の不確実性が高まっているため、1つの事業に注力するのではなく、多角化経営でリスクヘッジを図り、経営基盤の安定化を目指す企業も多い。事業の多角化による横展開はシナジー効果を生み出し、成長スピードの加速を促せるのも大きなメリットだ。
しかし、多角化経営で新規事業を立ち上げる場合、収益化まで時間を要したり失敗のリスクを伴うことで、投資家から肯定的な評価を得られないケースもある。
また、不確実性の高いVUCA時代では、革新的な技術が登場し、ビジネスモデルの変革を図るべくテクノロジードリブンに取り組む企業も多い。その一方で、テクノロジードリブンは投資家の理解を得るのが難しい傾向にあり、企業価値向上の機会が喪失されている。
中長期という時間軸の中で企業の稼ぐ力や、競争優位性を持続・強化し、投資家に対して具体的な戦略・ビジネスモデルを説明して理解を得ることが必要である。
新規事業創出やイノベーションに対する「種植え」に関する取組
検討会に参加した企業は、新規事業創出・イノベーションにつながる戦略や、利益を上げられていない新規事業について、投資家から積極的な評価がされていないことを問題点に挙げた。
また、VUCA時代においては本業から遠く、成功確度の低い新規事業も含めて、イノベーションを生み出すための取り組みが必要であると見解。
それに対し、投資家はトラックレコード(過去の実績や履歴)がなく、収益性を測れないため、成功確度やどの程度の市場成長を見込んでいるのかなど、具体的な説明がなければ積極的に評価できないと述べた。
過去の成功実績のない領域への投資は、投資家も二の足を踏むだろう。
このような観点から、トラックレコードのない取り組みであっても、企業と投資家が密に対話し、新規事業創出・イノベーションの評価を実施することが重要であるとした。
例えば、経営資源をいつ投入して種植えを行うのか、その種植えの将来的な成功確度や市場成長規模、リターンはどの程度を想定しているのかなど、投資家の疑問点への丁寧な説明が求められる。
そして、新規事業創出・イノベーションに関する種植えが、中長期的な企業価値の向上とどのような関係にあるのか、企業と投資家の間で共通認識を醸成し、議論を進めていくことが推進された。
ESG/SDGsなどの社会的価値と企業の稼ぐ力・競争優位性に基づく経済的価値の両立に向けた取組
ESG/SDGsや新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、企業に対する社会のサステナビリティへの貢献要請は拡大している。
ESGは、Environment(環境)Social(社会)Governance(ガバナンス)の3つの頭文字をとった言葉。気候変動や人種差別など数多くの課題を抱える中で、企業は、利益追求だけではなく、環境、社会、ガバナンスの3つの視点をもって事業に取り組むべきとという考え方。
SDGsは、「Sustainable Development Goals」の略で「持続可能な開発目標」と訳され、持続可能でより良い社会を実現するために、飢餓や環境、ジェンダーなど17の取り組むべき目標を定めた取り組み。2015年の国連サミットで採択され、世界的に関心が集まっている。
昨今のESG投資では、社会のサステナビリティに対応できていない企業を投資対象から外すネガティブ・スクリーンを採用しているが、本選定方法では、中長期的な新市場創出・獲得につながるオポチュニティを捉えることは困難。
リスクの側面に限らず、新市場創出・獲得に伴う企業成長の側面の両面を捉え、社会的価値と経済的価値を同期化することで、企業価値の向上を期待できるという認識を共有した。
SX(サステナビリティトランスフォーメーション)とDXの違い
SXと同様、経済産業省が2018年にその重要性を提言したのがDX(デジタルトランスフォーメーション)だ。DXとは、「AIやIotなど最新のデジタル技術を活用し、ビジネスや組織を変革して、競争力の維持・向上を図る」という意味で、主にビジネス領域で利用されている。
SXとDXは混同されるケースもあるが、大きな違いとしては時間軸が挙げられる。DXは新しいデジタル技術により、「短期的」なビジネスの競争優位性の確立が目的である一方で、SXは「中長期的」に持続的な企業価値の向上を目指す。
どちらの概念を重視すべきかは一概に言えないが、SXとDXを組み合わせた経営方針を策定することも重要とされている。例えば、DXで推進したビジネスモデルが短期的に軌道に乗った場合でも、デジタル技術や市場が早期に陳腐化すれば、企業の持続可能性は乏しいと言える。
しかし、SXを同時に推進することで、中長期的にサステナブルな組織を構築可能。SXをベースとして、DXを推進していくことが、不確実性の高い時代を生き抜く上で重要と考えられるだろう。
SX(サステナビリティトランスフォーメーション)の推進に重要なダイナミックケイパビリティとは?

SXを推進していくために欠かせないとされているのが、ダイナミックケイパビリティだ。ダイナミックケイパビリティとは、企業が激しいビジネス環境の変化をいち早く察知し、保有する経営資源を再結合・再編成して自己を変革する能力を指す。
不確実性の高い時代であっても、その都度環境に適合してビジネスを展開でき、持続可能性の高い経営にもつながる。ダイナミックケイパビリティを構成する要素としては、下記3つが存在する。
- 感知
- 捕捉
- 変容
ダイナミックケイパビリティにおける各要素の意味を見ていこう。
感知
感知とは、市場・競合他社・顧客ニーズなどビジネス環境の動向を分析し、脅威や危機を察知する能力を指す。
サステナブルな経営を目指すのであれば、環境の変化に応じて競争上の優位性を確立することが必要不可欠。環境の変化を常に観察し、時代に即した戦略を講じていくことが重要と言えるだろう。
捕捉
捕捉とは、企業の保有資源や知識、技術を機会に応じて、再構成・再利用する能力のことを指す。外的要因を的確に感知し、柔軟な対応を取ることが、捕捉力には求められている。
近年のビジネス環境は変化のサイクルが短く、従来の手法では通じないケースも多い。感知により収集したデータやICT技術なども活用しながら、企業内の資源を外部環境に沿って臨機応変に再構成し、持続可能な企業の構築につなげていきたい。
変容
変容とは、組織の資源を結合・再配置し、持続可能な競争の優位性を保つ能力を指す。外部環境に応じて、組織体制や内部ルールを変更することが重要。
また、組織の内部資源を継続的にマネジメントしていくことが、変容力の向上につながり、中長期的な競争優位性の確立も期待できる。
SX(サステナビリティトランスフォーメーション)の事例
ここでは、先行的にSXに取り組む企業として、日立エナジーを紹介する。
日立製作所は2050年までに、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルの達成を目標に掲げているが、その一環としてアメリカのABB社と事業融合し、日立エナジーを立ち上げた。日立エナジーは社会価値・環境価値・経済価値のバランスを取りながら、持続可能なエネルギー構築の取り組みを実施している。
また、事業融合したABB社は持続可能な未来の実現に向けて、社会と産業の変革に活力を与えていた企業。サステナビリティへの取り組みとして、太陽光エネルギーの開発・風力発電の導入を進めていた。ABB社と日立製作所の事業融合により、持続可能なエネルギーは一層普及し、SXの促進も期待できるだろう。
さらに、日立製作所のグループ会社になるが、ビジネスコンサルティング会社の日立コンサルティングは、SXの推進支援も実施している。持続可能な事業価値の創出を目指し、企業の価値観に沿った事業戦略の策定や、テクノロジーを活用した事業変革機会の導出など、SXの実現・実行をアプローチ。
他にも、SXの支援事業を展開する企業は複数存在するので、SX推進のためにコンサルティングを受けるのも1つと言えるだろう。
SX(サステナビリティトランスフォーメーション)のまとめ
SDGsと同じくして、その重要性が認知され始めているSX。サステナブルな企業価値の創出に伴う投資には、投資家から合意が得られないといった障壁もあったが、SXで企業と投資家の対話の必要性が具現化された。
また、SXは中長期的に見て、持続可能性を重視した経営方針を目標とするが、ビジネスモデルを変革することは容易ではない。経営陣が投資に責任ある決断力を持ち、従業員の理解も得ながら、経営方針・ビジネスモデルの変革を推し進めて欲しい。