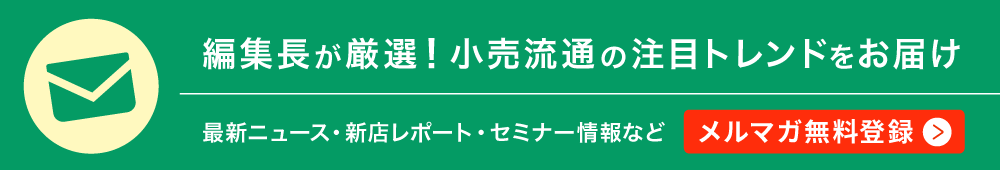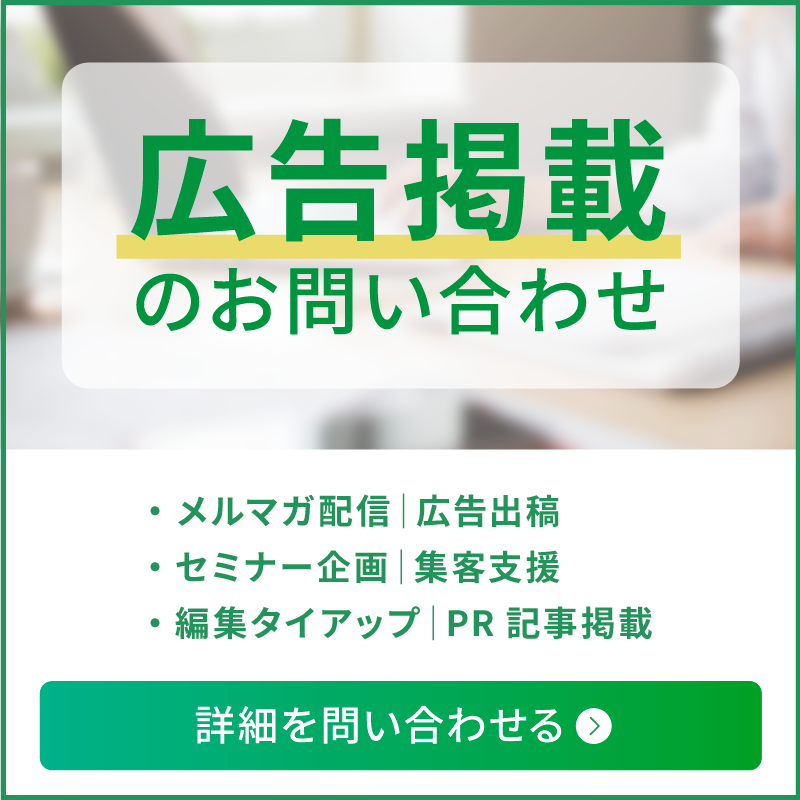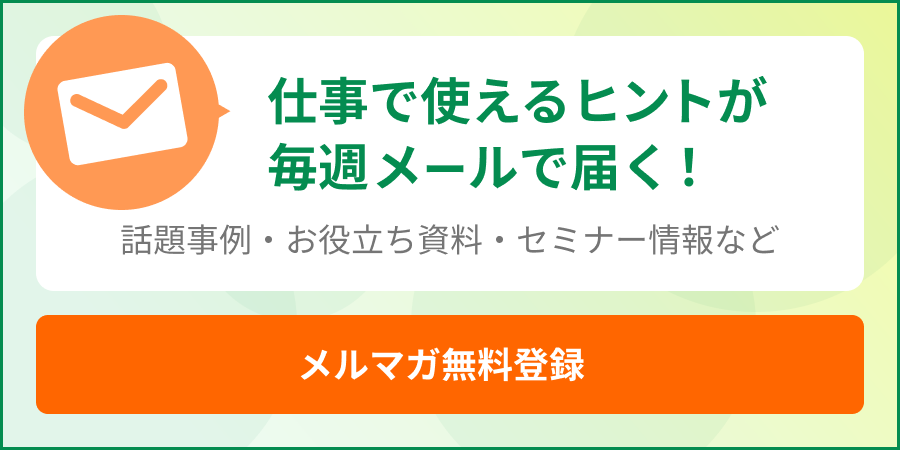- 連載:
- 食のトレンドウオッチ!
第2回 「Indulgence」が訳せない
2022.11.09
2022.04.18
いまの仕事を始めてからずっと悩んでいることがある。
「Indulgence」がうまく訳せないのだ。
私の仕事は世界の食品トレンドを日本の企業にお伝えし、商品開発やマーケティングに活用してもらうことである。世界の情報というのは基本的に英語だ。フレッシュな最新トレンドになればなるほど、情報源の大半は英語じゃないと手に入らない。
講演資料や展示会で掲示するパネルについては、できる限り日本語に訳すようにしている。しかし、ちょっと気取ったクールな英語表現を、翻訳ツールで直訳してしまうと、結局「なんのこっちゃ」になってしまうことが多い。これは翻訳のあるあるだろう。
だから私は前段階で、キートレンドや、製品ストーリーや、該当企業のミッションなど、その背景に想いを馳せるプロセスを踏む。さらに「むっちゃ素敵なストーリーやん」とか「その製品コンセプトはないやろ」とか「この視点めっちゃ笑えるがな」などと関西弁でとことんツッコミを入れる。
そうこうしているうちに、日本企業にいま伝えるべき「アハ!体験」はこれだ!というのが脳内に降臨してくるので、 その要点を一気に日本語化するのだ。ある意味、職人技かもしれない。
このやり方はそれなりにうまくいっており、翻訳作業ははかどるのだが、文中に「Indulgence」が登場すると状況が一変し、思考がフリーズしてしまう。「天敵現る」なのだ。
Indulgenceを辞書で調べると「ふけること、道楽、楽しみ、気ままにさせること、甘やかし、わがまま、大目に見ること、寛大」などと出てくる。シンプルに訳すと、ぜいたく感を味わえる食品、嗜好品といったところだ。でも何かが違う。自分としてこの訳には違和感がある。
英英辞典だと以下のように定義されている。
「an occasion when you allow someone or yourself to have something enjoyable, especially more than is good for you」
要するに、必ずしも栄養価が高いわけでもなく、体にも良いわけでもないが、味であったり食感であったり欲求面から思わず食べてしまう食品のことをいうらしい。
つい先日、各国のメンバーと社内勉強会に参加していて、Indulgenceが議題に上がった。そこで思ってもいなかった事実が判明した。実はこの言葉を訳しにくいのは日本語だけではなく、他の言語でも同様だったのだ。どこの国のマネージャーも困っていた。「ああ、悩んでいたのは俺だけじゃなかったのか」と少し安堵。
さらに興味深いのは、各文化圏によってIndulgenceに対して異なるイメージがあるということ。多くの人は、チョコレートやアイスクリームなどの甘い嗜好品をイメージするが、ピザやパスタやアルコールを含める人もいた。国によっては健康的な野菜や果物も、なんとIndulgenceと捉えるケースがあるらしい。

楽しさの象徴、または社交の場の賑わいなど、ポジティブなイメージを持つ人がいる一方、肥満につながる不健康なネガティブイメージを持っている人も多かった。
どんなものでも食べ始めは楽しいが、食べ続けるとどこかのタイミングで罪悪感が生まれる。お酒も少量なら楽しいが、飲み過ぎるとグダグダになる。Indulgenceは時間軸によってポジティブ→ネガティブが切り替わる、まるで七変化する舞台役者だ。
考えようによっては、繊細かつ微妙な感情を反映した言葉であり、青二才のAI(人工知能)翻訳ツールにはまだまだ訳すことのできない、人間が人間たる由縁の表現といえよう。
「Indulgenceを理解できれば、世界トレンドが見える」
とまでは思わないが、Indelgenceにまつわる人の感情を読み解ければ、食品開発に応用できそうだ。これからはこの言葉と仲良くしたい。